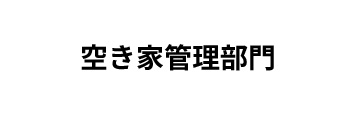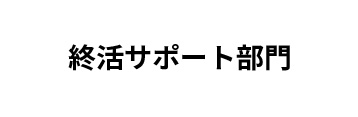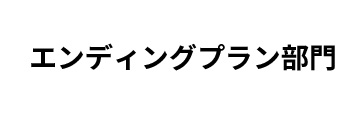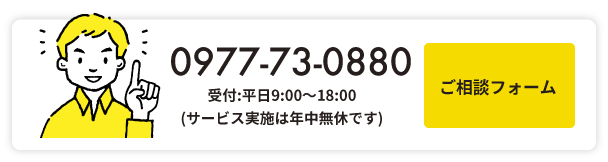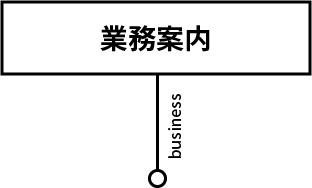

関連する
免許資格
福祉住環境コーディネーター2級
増改築相談員
2級建築士
2級建築施工管理士
住宅省エネルギー技能者(設計・施工)
赤外線建物診断アドバイザー
ハウスインスペクター
住宅建築コーディネーター

*国土交通省改修ガイドライン事例イメージより
身体の障がいや高齢化などで、家庭内での普段の生活に不便を感じる場面が多くなります。家の中の段差を解消したり、手すりを取り付けたりするようなことだけではなく、その人にとって最適な住環境はどのようなものか、何が必要なのかを専門的な視点で見極める必要があります。
本来であれば、行政機関や地域包括支援センターを通じて、要介護または要支援の認定を受けなければ、きめ細やかなサポートを受けることができません。
そこで、「Foryou」では、自然老化・病的老化・認知症等の心身機能の予備対策を中心として、不便や支障を感じておられる方に適切なアドバイスができるように福祉住環境整備事業を開始することにしました。
1.福祉住環境整備に関する相談援助
2.行政機関や地域包括支援センター等への連携
3.バリアフリーを基本とした住まいの考え方
4.対象者住居の現地調査
5.住宅改修に係る費用と補助金等の案内
6.介護認定を受けて福祉用具の活用
7.福祉住環境整備事業完了後のフォローアップ
| 「Foryou 」の福祉住環境コーディネーター・建築士・耐震診断士等の資格を所有した担当者が、個人情報の保護を厳守しながら、お一人お一人の状態に合わせた住環境を整えていきます。 医師や介護支援専門員等と情報共有が必要な場合は、事前に対象者様に確認しながら進めていきますのでご安心ください。 |  |
1.福祉住環境整備に関する相談援助
2.行政機関や地域包括支援センター等への連携
3.バリアフリーを基本とした住まいの考え方
4.対象者住居の現地調査
5.住宅改修に係る費用と補助金等の案内
6.介護認定を受けて福祉用具の活用
7.福祉住環境整備事業完了後のフォローアップ
「Foryou」の福祉住環境コーディネーター・建築士・耐震診断士等の資格を所有した担当者が、個人情報の保護を厳守しながら、お一人お一人の状態に合わせた住環境を整えていきます。
医師や介護支援専門員等と情報共有が必要な場合は、事前に対象者様に確認しながら進めていきますのでご安心ください。


脳血管障害などによる片麻痺の場合は、健側(障害のない側)に手すりを必要とするために、アプローチの両側に手すりを取り付けたり、通路の幅を広げて中央に手すりを設置する場合もあります。今の症状に合わせた判断だけではなく、今後予想される変化も考慮しながら対応していくことで、転倒などの危険から守ることにもなります。
道路から玄関ポーチまでのアプローチに高低差がある場合、スロープの設置か緩やかな階段のどちらを採用するかは、将来の身体状況を含め、慎重に判断しなければなりません(パーキンソン病の場合、スロープは適さないこともあります)。敷地に余裕がある場合は、階段とスロープを併設することが有効です。
玄関扉については、開き戸は引戸に比べて開閉の際の動作が多いため、特に高齢者はバランスを崩して転倒する危険があります。また、車いすの場合は、開閉の際に車いすの方向を変えなければならないため、狭いポーチでは操作が難しくなります。改修の際は、身体の移動操作が少なくて済むように引き戸に変更することも考えなければなりません。
通常、玄関土間部分は、玄関ポーチより一段高くなっています

これをできるだけ解消することが望ましいのですが、室内の温度を保ち、すきま風やほこり、雨水の侵入を防ぐためのものですので、玄関扉の下枠に最小限の段差ができることはやむを得ないところですが、玄関ポーチやアプローチなどの高低差は少しでも解消したいものです。
自立歩行の場合は、特別にスペースを拡げる必要はありませんが、つえ歩行の場合はつえをつくスペース、介助者歩行の場合は介助者のスペースを確保する必要があります。また、外出時に玄関で装具を装着する場合は、実際に装着動作を確認してもらいスペースを決定します。
車いすを自立して使用する場合の玄関土間スペースでは、車いすの通行幅員や、車いすの乗り換えのスペースだけでなく、玄関扉の開閉動作、上框(*あがりかまち:玄関の上がり口に横に通した化粧材横木)部分の昇降動作など、連続的な動作の流れを考慮して、必要なスペースを検討しなければなりません。
固定式のスロープが設置できない場合は、可動式スロープを用いて段差を解消します。
この場合、介助者による設置と取り外しが常に必要となるために、玄関周辺にスロープの収納場所を確保する必要があります。もちろん介助者が容易に持ち運びできるようにしなければなりません。
また、上框付近を安全に昇降する補助のために、縦手すりと横手すりの取り付けも検討します。
廊下は、寝室や居間などの居室と浴室・トイレなどの生活に不可欠な動線です

高齢者や障害者にとっては、廊下を自由に移動できるかどうかは、ふだんの住居内の生活に大きな影響を与えます。
長年住み続けた我が家であっても、加齢による運動機能の低下は、出入口のわずかな段差でつまずきやすくなり、車いす移動の場合は、廊下の幅やドアなどの開閉により移動が難しくなることがあります。
そのため、宅内では出入口部分の段差の解消だけではなく、廊下の幅員や建具の幅、戸の形状などにも配慮が必要となります。
一般的に畳床とフローリング床との厚さが異なるために、和室の床面は洋室の床面より15~45mmほど高くなっています。この段差こそ、高齢者や障害者にとってはつまずきによる転倒事故の大きな原因となります。
簡易的に敷居とフローリングの段差部分に、すりつけ板(*小さなスロープを作るために取り付けるくさび形の板)を設置する方法がありますが、この板の両端部につまずかないような配慮も必要です。
福祉住環境の観点からは、和室と洋室の床段差を解消する方法として、新築の場合には、洋室の床束(ゆかづか:床下に立てる短い柱)を長くする方法で、リフォームの場合は和室部分の床束を短くして洋室床面に合わせる方法が推奨されています。
室内の手すりは歩行や動作をサポートし、転倒を防ぎます

加齢に伴い身体機能が低下してくると、歩行時にからだのバランスを崩したり、室内のわずかな段差につまずいて転倒することが多くなります。戸の開閉動作時に、バランスをとろうと無意識に壁に手をついている高齢者も多く、これは脚が不安定なために自分のからだのバランスをとるための動きです。
その動きを補助するための手すりは、安全な歩行や移動を助けるといった役割があり、上肢を使って体位を安定させることができます。手すりは、門扉から玄関までのアプローチ、玄関、廊下、階段、洗面脱衣室、トイレなど室内のいたる箇所に設置されます。
手すりには、からだの位置を移動させるときに手を滑らせながら使用する「ハンドレール型」と、からだの位置はそれほど移動させないが、移乗動作や立ち座り動作のときに、しっかりと掴まって使用する「グラブバー型」があります。
リフォーム工事では、手すり受け金具を既存の間柱自体に取り付けることが多いのですが、指定のビスの本数を留めることができない場合は、十分な支持力が得られないので手すりの取り付けは避けるべきで、かえって危険な状態となってしまいます。
建具については、住宅内で使用される戸の幅は、その室内で行われる生活動作によって考え方が異なってきます。
玄関は荷物を持っての出し入れや、複数の家族が同時に利用することが考えられることから、住宅内の他の戸に比べ、幅が広いものが使用されています。一方、浴室やトイレは、基本的に個人で使用することが多いプライベートな空間のため、室内スペースは他室と比べ狭く、戸の付近も狭い構造となっています。しかし、高齢者や障害者が住宅内で介助歩行やつえ歩行をする場合には、通常の戸の幅員では使いにくい状態となります。
また、建具の下部のわずかな敷居段差も、高齢者や障害者の移動の妨げとなりますので改修の際は慎重に考えていくことが必要です。
トイレや浴室には細やかな心づかいが必要です

加齢にともなって、立ち座りの動作がきつくなると、慣れ親しんでいた和式便器から洋式への交換が必要となります。
また、高齢者はトイレの使用頻度が多くなりますので、夜間に暗い廊下を歩いてつまずいたりしないよう、トイレまでの動線における住環境をいろいろと整備する必要があります。
トイレに関わる不便・不自由な状況は、相談しづらいデリケートな内容です。
特に女性の場合は、本人の悩みを細かく聞き出しにくく、動作方法も本人以外は把握しづらいものです。十分な配慮がなされないままだと、楽なベッド回りでの簡易トイレの使用になることで、次第に寝たきりの生活へとつながりかねませんので特に注意と配慮が必要です。
脳血管障害による片麻痺者の場合には、麻痺側に介助者が立って介助をすることを原則とします。これは、バランスを崩して麻痺側にからだが傾いたときに、転倒しないよう支えますが、一方の健側(麻痺のない側)では手すりに掴まってからだを安定させることで排泄行為に影響を与えないようにします。
関節リウマチや骨折などにより股関節の動きに支障がある場合や、膝関節・股関節等に痛みを伴う場合には下肢を曲げにくくなりますので、便座面の高さを高く設定する必要があります。
浴室は通常、狭く・濡れて滑りやすいので、戸の開閉・浴室内の移動・浴槽への出入り・洗体・水栓金具の操作など、高齢者や身障者にとってはとても複雑な動きとなるため、それぞれにかなりの工夫が求められますので、慎重に整備内容を検討する必要があります。
敷地に余裕がある場合には、車いす使用や介助者のために、外に浴室スペースを増築する事例も多く見受けられますが、最近はバリアフリーに対応したユニットバスが一般的となり、住宅機器メーカーのショールームで実際に入浴動作を試しながら、広さや浴槽の形状や設備など、それぞれの利用者の条件に合ったものを選択することもできます。


地元産品ショップ
Copyright (C) 2021 For you Corporation. All Rights Reserved.